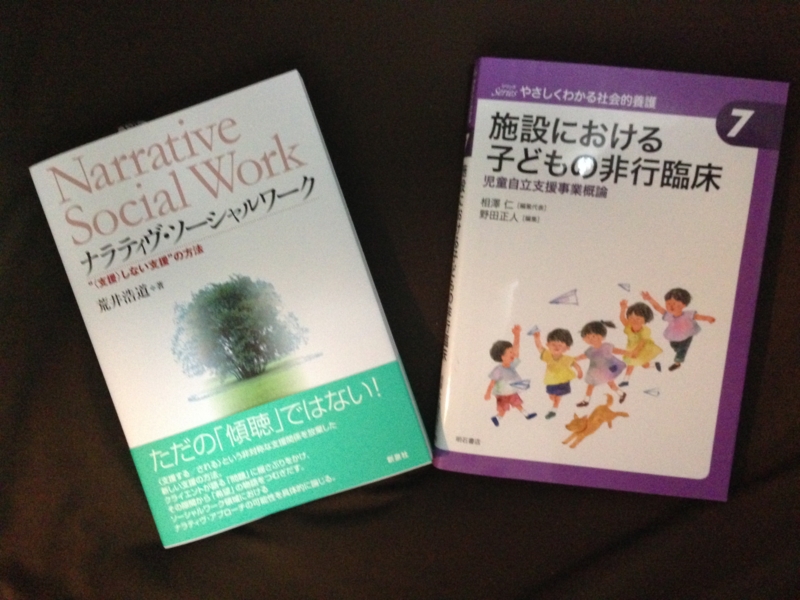親の資格ってなんだろう。
厚木の衰弱死の件。facebookでも触れたけど、いつものお決まりの展開過ぎて、脱力してしまう。
親の資格ってなんだ?親だって人間、凹むこともあるし、逃げたくなる時もある。
親を責めるのは簡単だけど、親を責めて果たして解決する問題なのだろうか。
親に心の隙間があったからこそ起きたのではないか。その隙間を過激に突いたとしても、
満たされることはあったのだろうか。子育てへの、あるいは子どもとの関わりへの意欲は湧くだろうか。
何がそろっていれば、親の資格があるのだろうか。教えてほしい。
資格があるから親になるわけではない。
ベビーカー論争に思うこと。
NHKのNEWSWEBにこんな記事がUPされていた。
「ベビーカーマーク」作成 交通機関などに (記事はこちら)
ベビーカーに子どもを乗せた親が交通機関を気兼ねなく利用できるようにしようと、国土交通省の検討会が「ベビーカーマーク」を作成しました。今後、電車やバスの車内のほか駅などに貼って、周りの利用者にベビーカーへの配慮を求めていくことにしています。
(中略)
専門家「きちんとスペース確保を」
恵泉女学園大学教授で、子育て支援に取り組むNPOの代表を務める大日向雅美さんは、「ベビーカーを乗せて非常識だと思われるのではないかと心配している母親がたくさんいるので、マークが貼られて、ベビーカーで乗っていいということがはっきりと分かるようになることは大きな進歩だ。ベビーカーが乗ってきたら手を差し伸べ、みんなで助け合うひとつのきっかけになってほしい」と評価しました。
そのうえで、「ベビーカーは大きく重量もあり、中に赤ちゃんがいる。どこに置いてもいいというわけではないので、マークを作成するのであれば、きちんとスペースを確保しベビーカーを固定する装置もつける必要がある」と話しています。
NHK NEWSWEB 3/26 18:56 配信記事
ベビーカーに対する風当たりって想像以上に強い。中でも、混んでいる時間(朝夕の通勤・通学・帰宅の時間帯)に乗ってくるのは、いかがなもんかというご意見をお持ちの方、結構いらっしゃるのでは。とはいえ、朝夕の時間が混むのには、それこそ人それぞれの事情があり、そうなっているわけで、一方的にベビーカーを使ってる人だけに「配慮」を求めるのは、何だか不公平。お互いさまというか、できる範囲で心配りが循環するような社会のあり方がマナーが必要なのではないだろうか。
時短勤務もあるんだからそれ使えばいいのでは?という意見もちらほら。職場で、時短勤務に対する理解が十分醸成されていれば問題ないのだろう。ただ、現状では、そうした職場は限定的ではないだろうか。少しでも会社に貢献するために、朝だけは早く行って、夕方少しだけ早めに帰らせてもらうようなとり方をしている友人が自分の周りには多い。本当は通勤時間を外して送迎したいとは考えているけど、なかなか難しいという声もあった。
人にはそれぞれ事情がある。いちいち気にしていてはしょうがない、あるいは自分のことで精いっぱい、という余裕のない空気感が日本社会全体に蔓延していないだろうか。ベビーカーを巡る論争、時短を巡る論争は最近よく見かけるが、論争の根っこには、そうした日本社会のゆとりのなさがあるのではないだろうか。できることを、できる範囲で、さりげなくできるそんな空気感を醸成できたらいいのになあ。
聴くこと・語ること・向き合うこと
もうちょっと前にこの本と出会っていればなー。読後の独り言。
荒井浩道先生が書かれた「ナラティヴ・ソーシャルワーク―“〈支援〉しない支援"の方法」を一通り読み終え、過去の自分の体験と重ね合わせる。「そうか、それはうまくいかなかったはずだ」と反省というか後悔の思いを想起。そして今自分が関わっている活動・研究にあてはめ、多々思いを巡らせる時間を頂いた。
困難事例、多問題家族、限界集落というラベリングによる先入観。それが「問題」を強化しかねないのだということを改めて教えて下さった。

- 作者: 荒井浩道
- 出版社/メーカー: 新泉社
- 発売日: 2014/02/18
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
少し前の話ですが、学生時代、障害学生「支援」に携わっていた時期があります。以前もブログで数度にわたり、その時の思いなどを綴っています。そこではあまり直接的には触れませんでしたが、今振り返ると、当時、なかなか進まない環境づくりに、重苦しさを感じまくっていたなと思います。それは、別の立場に身を置く今の職場でも感じていますが。
当事者である学生、直接サポートする学生、大学側と向き合い間接的にサポートする学生、それ以外の学生さん、親御さん、大学側、様々な関係者の中で右往左往していました。何をどう前に進めるべきか、ときには方向感覚すら失いがちになりながら、しかし、環境づくりのはじめの一歩を踏み出せるよう、努めてきました。もちろん、失敗に終わったアプローチもかなりあります。
一番困ったのは、当事者である学生さんの声の集約です。大学としてよりよい環境整備を進めるためには、それなりの声の集約と共有が不可欠です。
何か問題を抱え、困っていたとしても、その声が小さく、一定程度の共有が図られていないと環境の向上にはつながりません。大学は多数の人がそれぞれの役割を果たすべく、日々動いています。週に10コマの授業をとれば、のべ10人の教員が携わり、事務室には事務職員がいて、施設の維持管理にあたる人たちがいます。
大学として障害学生支援に取り組もうとなると、様々な役割をもつ多くの人との「問題」の共有が図られなければなりません。そんな多くの人と関わることは、学生さん1人では体力も気力も持ちません。
もし、1対1で、その場限りの支援を構築できたとしても、築かねばならない関係が多すぎたり、職員の異動等で支援関係は消失したりするという場合もあります。最近では、そうした学生側の負担を減らすために、「障害学生支援室」などといった組織を設けているところもあります。
ところが、そういた組織の設置やノウハウの蓄積、支援体制の構築までに、そして環境整備をより前に進めるためには、一定程度の声の共有が必要になってきます。環境の整備には経済的なコストや人的、時間的なコストが発生します。そうしたコストがかかることの負担感もあって、障害学生がスムーズに支援を受けられるとは限らないケースもあります。
これを打破するためには、同じように困っている学生さんの声を集約することが挙げられます。「困っているのは、私だけではない」という声が多ければ、大学としても、より効果的な支援や環境整備の必要性を感じるでしょう。
もう1つ、多様な学生との声の共有です。支援を必要とする学生さんだけの声では、環境づくりという意味では不十分です。支援に携わる学生、支援に携わらない学生、それぞれの学生さんとの声の共有が必要になってきます。これはとてもエネルギーを必要とします。特に今まで問題と思っていない、その問題が身近でない学生さんに、「問題」として共有してもらうわけですから、その働きかけには工夫を要します。
なぜ、支援に携わる学生さんだけでなく支援に携わらない学生さんとの共有が必要なのでしょうか。学生さんはどんどん入れ替わっていきます。学年を経るとともに、学びの集団もそのメンバーが入れ替わります。例えば、1,2年生では語学のクラスがあったり、3、4年生ではゼミがあったりします。大学の規模にもよりますが、授業、クラスのメンバーの構成は変わるので、当事者学生はそのたびに、新たに関係性を築くことが必要になってきます。今現在は支援に関わらなくても、いつそういう場面に遭遇するかはわからないのです。大学の側から言っても、学生全体の問題意識の向上は、支援環境の継続的な整備には必要不可欠です。これがないと、一部の支援学生に負担がかかり、もしその支援学生に何かあった場合の対応が難しくなるリスクがあるからです。
声の集約と共有の必要性について触れましたが、先にも綴った通り、学生時代四苦八苦しました。単に私個人の問題であるとは思うのですが。学生時代は、当事者学生でもあり、当事者を直接的にサポートする学生でもありました。そして、大学側と向き合い間接的にサポートする学生でもありました。とてもわかりづらい立場だったと言えます。そうなったのにはいろんな事情がありますが(笑)
わかりづらい立場であるが故に、失敗してしまったことがあります。それは声の集約です。声の集約の必要性を何となくわかっていたがために、懇談の場で十分に当事者や支援学生の言葉を引き出すことができなかったように思います。当事者としての思い、サポート学生としての思い、大学側の意図もそれなりに理解していた中では、自分自身の心の中に、様々な思いが湧き出してしまい、十分ファシリテートができませんでした。そう「無知の姿勢」を貫くことができなかったのです。早く問題を解決したいという思いと同時にそうした声を共有するという貴重な場であるという思い、この2つをうまくバランスをとることができなかったのだと今振り返ると思います。
さいごに、もう1つ考えなくてはいけないのは、「支援」を必要としない学生さんの存在です。「声なき声」と言ってもいいでしょうか。大学には、障害学生と言っても、その障害は多様です。大学では担いきれない支援を必要としている学生もいれば、支援を否定する学生さんもいます。そうした学生さんの思いを聴くことによって、新たな問題、支援のあり方、大学とは何か、教育とは何かという課題の一端が見えることがあります。
最近では、いわゆる面倒見の良い大学を標榜する大学も増えていますが、学生さんとの語りの中で、大学としての支援、学生さんとの関わりのあり方を、日々見つめ直していかなくてはいけないなとこの本を出会ったことで、気づかされました。
聴くこと・語ること・向き合うこと
もうちょっと前にこの本と出会っていればなー。読後の独り言。
荒井浩道先生が書かれた「ナラティヴ・ソーシャルワーク―“〈支援〉しない支援"の方法」を一通り読み終え、過去の自分の体験と重ね合わせる。「そうか、それはうまくいかなかったはずだ」と反省というか後悔の思いを想起。そして今自分が関わっている活動・研究にあてはめ、多々思いを巡らせる時間を頂いた。
困難事例、多問題家族、限界集落というラベリングによる先入観。それが「問題」を強化しかねないのだということを改めて教えて下さった。

- 作者: 荒井浩道
- 出版社/メーカー: 新泉社
- 発売日: 2014/02/18
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (3件) を見る
少し前の話ですが、学生時代、障害学生「支援」に携わっていた時期があります。以前もブログで数度にわたり、その時の思いなどを綴っています。そこではあまり直接的には触れませんでしたが、今振り返ると、当時、なかなか進まない環境づくりに、重苦しさを感じまくっていたなと思います。それは、別の立場に身を置く今の職場でも感じていますが。
当事者である学生、直接サポートする学生、大学側と向き合い間接的にサポートする学生、それ以外の学生さん、親御さん、大学側、様々な関係者の中で右往左往していました。何をどう前に進めるべきか、ときには方向感覚すら失いがちになりながら、しかし、環境づくりのはじめの一歩を踏み出せるよう、努めてきました。もちろん、失敗に終わったアプローチもかなりあります。
一番困ったのは、当事者である学生さんの声の集約です。大学としてよりよい環境整備を進めるためには、それなりの声の集約と共有が不可欠です。
何か問題を抱え、困っていたとしても、その声が小さく、一定程度の共有が図られていないと環境の向上にはつながりません。大学は多数の人がそれぞれの役割を果たすべく、日々動いています。週に10コマの授業をとれば、のべ10人の教員が携わり、事務室には事務職員がいて、施設の維持管理にあたる人たちがいます。
大学として障害学生支援に取り組もうとなると、様々な役割をもつ多くの人との「問題」の共有が図られなければなりません。そんな多くの人と関わることは、学生さん1人では体力も気力も持ちません。
もし、1対1で、その場限りの支援を構築できたとしても、築かねばならない関係が多すぎたり、職員の異動等で支援関係は消失したりするという場合もあります。最近では、そうした学生側の負担を減らすために、「障害学生支援室」などといった組織を設けているところもあります。
ところが、そういた組織の設置やノウハウの蓄積、支援体制の構築までに、そして環境整備をより前に進めるためには、一定程度の声の共有が必要になってきます。環境の整備には経済的なコストや人的、時間的なコストが発生します。そうしたコストがかかることの負担感もあって、障害学生がスムーズに支援を受けられるとは限らないケースもあります。
これを打破するためには、同じように困っている学生さんの声を集約することが挙げられます。「困っているのは、私だけではない」という声が多ければ、大学としても、より効果的な支援や環境整備の必要性を感じるでしょう。
もう1つ、多様な学生との声の共有です。支援を必要とする学生さんだけの声では、環境づくりという意味では不十分です。支援に携わる学生、支援に携わらない学生、それぞれの学生さんとの声の共有が必要になってきます。これはとてもエネルギーを必要とします。特に今まで問題と思っていない、その問題が身近でない学生さんに、「問題」として共有してもらうわけですから、その働きかけには工夫を要します。
なぜ、支援に携わる学生さんだけでなく支援に携わらない学生さんとの共有が必要なのでしょうか。学生さんはどんどん入れ替わっていきます。学年を経るとともに、学びの集団もそのメンバーが入れ替わります。例えば、1,2年生では語学のクラスがあったり、3、4年生ではゼミがあったりします。大学の規模にもよりますが、授業、クラスのメンバーの構成は変わるので、当事者学生はそのたびに、新たに関係性を築くことが必要になってきます。今現在は支援に関わらなくても、いつそういう場面に遭遇するかはわからないのです。大学の側から言っても、学生全体の問題意識の向上は、支援環境の継続的な整備には必要不可欠です。これがないと、一部の支援学生に負担がかかり、もしその支援学生に何かあった場合の対応が難しくなるリスクがあるからです。
声の集約と共有の必要性について触れましたが、先にも綴った通り、学生時代四苦八苦しました。単に私個人の問題であるとは思うのですが。学生時代は、当事者学生でもあり、当事者を直接的にサポートする学生でもありました。そして、大学側と向き合い間接的にサポートする学生でもありました。とてもわかりづらい立場だったと言えます。そうなったのにはいろんな事情がありますが(笑)
わかりづらい立場であるが故に、失敗してしまったことがあります。それは声の集約です。声の集約の必要性を何となくわかっていたがために、懇談の場で十分に当事者や支援学生の言葉を引き出すことができなかったように思います。当事者としての思い、サポート学生としての思い、大学側の意図もそれなりに理解していた中では、自分自身の心の中に、様々な思いが湧き出してしまい、十分ファシリテートができませんでした。そう「無知の姿勢」を貫くことができなかったのです。早く問題を解決したいという思いと同時にそうした声を共有するという貴重な場であるという思い、この2つをうまくバランスをとることができなかったのだと今振り返ると思います。
さいごに、もう1つ考えなくてはいけないのは、「支援」を必要としない学生さんの存在です。「声なき声」と言ってもいいでしょうか。大学には、障害学生と言っても、その障害は多様です。大学では担いきれない支援を必要としている学生もいれば、支援を否定する学生さんもいます。そうした学生さんの思いを聴くことによって、新たな問題、支援のあり方、大学とは何か、教育とは何かという課題の一端が見えることがあります。
最近では、いわゆる面倒見の良い大学を標榜する大学も増えていますが、学生さんとの語りの中で、大学としての支援、学生さんとの関わりのあり方を、日々見つめ直していかなくてはいけないなとこの本を出会ったことで、気づかされました。
支えること、助けること、寄り添うこと
大変遅くなりましたが、年明け初の更新です。本年も不定期更新になりそうですが、お付き合い頂けると幸いです。
年末から年始にかけて、シラバスの作成、卒論指導、レポートの添削、試験の作成、そしてセンター試験と立てつづけての業務に追われ、じっくり何かを考える、深める時間を持つことができずにいました。センター試験も無事済んだということで、やっと一段落。NPOの方も、新団体への移行に伴う諸業務、新規事業の構想・具体化などがあり、バタバタした日々を過ごしています。
家庭・子育てはといえば、年末年始、子どもたちは元気に過ごしていました。インフルもノロにも罹患することなく、無事乗り切った感じです。
年末年始は、様々な業務の合間を縫って、勉強会、研修会に参加する機会が多くありました。年末年始は、児童自立支援施設出身者の会の勉強会、男性保育士の勉強会、少年院出院者の方々の集まり、障害児学童保育に携わるNPOの勉強会・・・。素敵な出会い、学び、交流の場に参加でき、とても有意義でした。
そして、本日は1月20日。2014年は初めてのタイガーマスク基金の勉強会に参加させて頂きました。そもそもというか・・・いい加減会員になろう!という思いはあるのですが、もう少し落ち着いてから、振込の時間、郵送の時間を確保できたら、すぐ申し込もうと考えています。
勉強会で、タイガーマスク基金の理事の方々が「子どもたちに、寄り添うということ」をテーマに社会的養護や施設の現状、課題等々熱く語られていました。いろいろ思うところはあるのですが、年末年始に参加した勉強会での議論も併せて、「児童(家庭)福祉」の意味や社会的養護を巡る議論のあり方について、綴ってみたいと思います。
私が人生において、福祉に生涯関わろうと思ったのにはいくつか理由がありますが、一番の理由は「自分と同じ思いをしてほしくない。」ということです。後ろ向きですよね・・・。ともすれば、福祉を否定すらしかねない、そんな理由です。施設や里親など、児童福祉の措置制度の中で放浪していたとき、私は、福祉という言葉の恩着せがましい感じと尊大なイメージに嫌悪感を強く引き摺っていました。言葉だけでなく、福祉施設・制度の不自由さ、理不尽さにいら立ってもいました。そのいら立ちは、何なのか、大学に入り、福祉の勉強を少しするようになって、「福祉が人を殺す時」という本と出会いました。出会った瞬間、自分を取り巻く福祉の現状を言い表すのにぴったりなタイトルだと思ったものです。
その否定的感情の一方で、福祉施設にも福祉制度にも「日常」がある。他愛もないことかもしれないけれど、否定的に、一方的に時には断片的に語られがちな「福祉のある生活」を日常という視点から捉え直すことの必要性も感じていました。家庭的ではない環境かもしれない、借り物の環境かもしれないけれど、そこには日常がある。何気ない日常を大事にすることによって、福祉のあり方を変えられるのではないか、そう思う自分もありました。
社会的養護の議論の中で、施設養護と里親は対立するかのごとく、語られることがしばしばあります。児童福祉を専門に研究されている人や、現場に関わる人でさえ、対立を煽るかのようなことを言われる方もいらっしゃいます。
日本は施設養護が中心だが、世界は里親が中心だから日本も里親を推進していくべきだという主張はよく聞かれます。児童は家庭的環境で育つことが望ましい、そうした思想が根底にあるのですが、その思想の主語は、たいてい大人です。施設養護と家庭的養護(里親)が対立的に捉えられる今日においては、家庭的養護、つまり里親になじめない子どもの存在、里親の養育ではカバーしきれない子どもは、結局施設に放り込まれ、「隔離」されることになります。結局、よりしんどさを強く、多く抱える子どもが、家庭的環境から隔離されることになります。しかし、そうした子どもたちには家庭的環境は必要ないのでしょうか?
今日の社会的養護、とりわけ家庭的環境の必要性が 特定の意図を持ってその必要性が論じられているのではないか、そんな懸念を持たざるを得ません。本来、施設養護も里親も親御さんを中心にしたニーズがあって、あるいは明確な目的、存在意義があって成り立っています。そこのところは、児童福祉法に明確に規定されているわけですが、児童福祉法には、どこにも互いを否定し合うために各々の施設・制度が存在するとは書かれていません。本来、児童の福祉や自立に資するための制度のはずです。お互いの基盤は共通のはずなのに対立する、これははっきり言って、「大人の事情」でそうなっているとしか思えないのです。子どもたちやその家庭の現状等を踏まえ、「措置」がなされるわけで、今の議論のあり方は、どこか不毛な感じがします。
子どもたちを支える、寄り添う。言葉にすると穏やかな感じがしますが、現実はそうでもありません。子どもも、職員も、いろいろぶつかりあったりしますし、時には安全確保も図らなくてはなりません。
支える、支援するということは、まず「子どもの思いを聴く」ということから始まります。専門職たる人たちは、課題や現状を分析することをよくします。しかし、ともすればその分析がただの枠にはめ込めるかどうかといったものに陥ることがあります。しかし、専門職は、特定の援助技術や知見の専門家ではありますが、目の前の子どもの専門家ではありません。だからこそと言っていいかもしれませんが、入所/措置当初は、子どもの思いの表現が、大人にうまく伝わらないことや、認識のズレから生じる誤解などで、パニックになったり、ぶつかりあうことがよくあります。なかなか意思疎通ができず、不幸な状況を招くことさえあります。支えることも寄り添うことも、人と人とのつながりの中での関係性の一部です。つながりが切れることも、こじれることも当然あります。
振り返れば、私も児童福祉の各種施設に入所していた時や里親委託されていた時に、こいつら(職員)は、親でもないくせにエラそうな、わかったようなクチききやがってと思ったこともありました。仕事として向き合ってくることへの怒り、悔しさと言い換えてもいいかもしれませんが、とともに、土足で踏み入ってきて、あーでもない、こーでもないと絡んでくることへの強烈な嫌悪感の2つが混じりあった感情を持て余していました。先日の児童自立支援施設、少年院で過ごした経験を持つ仲間たちとの語らいの中でも、その複雑な感情について共有できました。
そうした感情を消化できずに、あるいは入所前のしんどさをうまく解消できずにいる人たちがいる、それが、さぼりがちだった大学での学びの中で感じたことでした。単に、施設や里親、そして社会の仕組みに迎合しろという意味ではありません。子どもの声を聴くということを、いろんなアプローチで行うことができれば、自分と同じ思いをせずに済むのではないかということです。そうすることによって、施設も里親も、あるいは家庭や地域社会、社会の仕組みも変えられるのではないか、そう考えています。
ちょっと時間も遅くなったので、この辺にしておきます。こっそり加筆するかもしれませんが、ご容赦ください。
支えること、助けること、寄り添うこと
大変遅くなりましたが、年明け初の更新です。本年も不定期更新になりそうですが、お付き合い頂けると幸いです。
年末から年始にかけて、シラバスの作成、卒論指導、レポートの添削、試験の作成、そしてセンター試験と立てつづけての業務に追われ、じっくり何かを考える、深める時間を持つことができずにいました。センター試験も無事済んだということで、やっと一段落。NPOの方も、新団体への移行に伴う諸業務、新規事業の構想・具体化などがあり、バタバタした日々を過ごしています。
家庭・子育てはといえば、年末年始、子どもたちは元気に過ごしていました。インフルもノロにも罹患することなく、無事乗り切った感じです。
年末年始は、様々な業務の合間を縫って、勉強会、研修会に参加する機会が多くありました。年末年始は、児童自立支援施設出身者の会の勉強会、男性保育士の勉強会、少年院出院者の方々の集まり、障害児学童保育に携わるNPOの勉強会・・・。素敵な出会い、学び、交流の場に参加でき、とても有意義でした。
そして、本日は1月20日。2014年は初めてのタイガーマスク基金の勉強会に参加させて頂きました。そもそもというか・・・いい加減会員になろう!という思いはあるのですが、もう少し落ち着いてから、振込の時間、郵送の時間を確保できたら、すぐ申し込もうと考えています。
勉強会で、タイガーマスク基金の理事の方々が「子どもたちに、寄り添うということ」をテーマに社会的養護や施設の現状、課題等々熱く語られていました。いろいろ思うところはあるのですが、年末年始に参加した勉強会での議論も併せて、「児童(家庭)福祉」の意味や社会的養護を巡る議論のあり方について、綴ってみたいと思います。
私が人生において、福祉に生涯関わろうと思ったのにはいくつか理由がありますが、一番の理由は「自分と同じ思いをしてほしくない。」ということです。後ろ向きですよね・・・。ともすれば、福祉を否定すらしかねない、そんな理由です。施設や里親など、児童福祉の措置制度の中で放浪していたとき、私は、福祉という言葉の恩着せがましい感じと尊大なイメージに嫌悪感を強く引き摺っていました。言葉だけでなく、福祉施設・制度の不自由さ、理不尽さにいら立ってもいました。そのいら立ちは、何なのか、大学に入り、福祉の勉強を少しするようになって、「福祉が人を殺す時」という本と出会いました。出会った瞬間、自分を取り巻く福祉の現状を言い表すのにぴったりなタイトルだと思ったものです。
その否定的感情の一方で、福祉施設にも福祉制度にも「日常」がある。他愛もないことかもしれないけれど、否定的に、一方的に時には断片的に語られがちな「福祉のある生活」を日常という視点から捉え直すことの必要性も感じていました。家庭的ではない環境かもしれない、借り物の環境かもしれないけれど、そこには日常がある。何気ない日常を大事にすることによって、福祉のあり方を変えられるのではないか、そう思う自分もありました。
社会的養護の議論の中で、施設養護と里親は対立するかのごとく、語られることがしばしばあります。児童福祉を専門に研究されている人や、現場に関わる人でさえ、対立を煽るかのようなことを言われる方もいらっしゃいます。
日本は施設養護が中心だが、世界は里親が中心だから日本も里親を推進していくべきだという主張はよく聞かれます。児童は家庭的環境で育つことが望ましい、そうした思想が根底にあるのですが、その思想の主語は、たいてい大人です。施設養護と家庭的養護(里親)が対立的に捉えられる今日においては、家庭的養護、つまり里親になじめない子どもの存在、里親の養育ではカバーしきれない子どもは、結局施設に放り込まれ、「隔離」されることになります。結局、よりしんどさを強く、多く抱える子どもが、家庭的環境から隔離されることになります。しかし、そうした子どもたちには家庭的環境は必要ないのでしょうか?
今日の社会的養護、とりわけ家庭的環境の必要性が 特定の意図を持ってその必要性が論じられているのではないか、そんな懸念を持たざるを得ません。本来、施設養護も里親も親御さんを中心にしたニーズがあって、あるいは明確な目的、存在意義があって成り立っています。そこのところは、児童福祉法に明確に規定されているわけですが、児童福祉法には、どこにも互いを否定し合うために各々の施設・制度が存在するとは書かれていません。本来、児童の福祉や自立に資するための制度のはずです。お互いの基盤は共通のはずなのに対立する、これははっきり言って、「大人の事情」でそうなっているとしか思えないのです。子どもたちやその家庭の現状等を踏まえ、「措置」がなされるわけで、今の議論のあり方は、どこか不毛な感じがします。
子どもたちを支える、寄り添う。言葉にすると穏やかな感じがしますが、現実はそうでもありません。子どもも、職員も、いろいろぶつかりあったりしますし、時には安全確保も図らなくてはなりません。
支える、支援するということは、まず「子どもの思いを聴く」ということから始まります。専門職たる人たちは、課題や現状を分析することをよくします。しかし、ともすればその分析がただの枠にはめ込めるかどうかといったものに陥ることがあります。しかし、専門職は、特定の援助技術や知見の専門家ではありますが、目の前の子どもの専門家ではありません。だからこそと言っていいかもしれませんが、入所/措置当初は、子どもの思いの表現が、大人にうまく伝わらないことや、認識のズレから生じる誤解などで、パニックになったり、ぶつかりあうことがよくあります。なかなか意思疎通ができず、不幸な状況を招くことさえあります。支えることも寄り添うことも、人と人とのつながりの中での関係性の一部です。つながりが切れることも、こじれることも当然あります。
振り返れば、私も児童福祉の各種施設に入所していた時や里親委託されていた時に、こいつら(職員)は、親でもないくせにエラそうな、わかったようなクチききやがってと思ったこともありました。仕事として向き合ってくることへの怒り、悔しさと言い換えてもいいかもしれませんが、とともに、土足で踏み入ってきて、あーでもない、こーでもないと絡んでくることへの強烈な嫌悪感の2つが混じりあった感情を持て余していました。先日の児童自立支援施設、少年院で過ごした経験を持つ仲間たちとの語らいの中でも、その複雑な感情について共有できました。
そうした感情を消化できずに、あるいは入所前のしんどさをうまく解消できずにいる人たちがいる、それが、さぼりがちだった大学での学びの中で感じたことでした。単に、施設や里親、そして社会の仕組みに迎合しろという意味ではありません。子どもの声を聴くということを、いろんなアプローチで行うことができれば、自分と同じ思いをせずに済むのではないかということです。そうすることによって、施設も里親も、あるいは家庭や地域社会、社会の仕組みも変えられるのではないか、そう考えています。
ちょっと時間も遅くなったので、この辺にしておきます。こっそり加筆するかもしれませんが、ご容赦ください。